イントロダクション
2021年2月28日にリリースされたSEEDAの「Nakamura (Remix) [feat. ralph, Kraftykid]」は、日本とイギリスのヒップホップシーンを繋ぐ画期的なコラボレーションとして注目を集めた楽曲です。レジェンドSEEDAが2020年12月に発表した「Nakamura」を、日本のグライム/ドリルシーンを代表するralphと、本場ロンドンのラッパーKraftykidを迎えてリミックスした本作は、国境を越えたドリルミュージックの可能性を示しています。
オリジナル「Nakamura」について
楽曲の背景
2020年12月にリリースされたオリジナルの「Nakamura」は、SEEDAがドリルミュージックに挑戦した意欲作です。プロデュースはghostpopsが担当し、BACHLOGICがミックスとマスタリングを手掛けました。
曲名の「Nakamura」は、日本の紙幣に描かれている福沢諭吉を連想させるフレーズとともに使われており、金銭やストリートでの成功をテーマにした攻撃的な楽曲となっています。SEEDAの日本語と英語を織り交ぜたバイリンガルラップが、ドリルビートの上で炸裂する様は圧巻です。
リミックスバージョンの誕生
制作陣
リミックスバージョンの制作には以下のメンバーが参加しています:
- プロデューサー: ghostpops
- ミックス・マスタリング: BACHLOGIC
- リリック: ralph, Kraftykid, DOT.KAI., SEEDA
- ミュージックビデオ監督: MESS (RepYourSelf)
- 撮影: D (RepYourSelf)
- 衣装: Awesome boy, kZm
- メイクアップアーティスト: 薗部聖奈
リリース情報
2021年2月28日にCONCRETE GREENレーベルから配信リリースされ、同日にミュージックビデオがYouTubeで公開されました。iTunes Storeのヒップホップ/ラップ部門では、日本で16位を記録するなど、高い評価を受けています。
参加アーティスト紹介
SEEDA
東京都出身で、幼少期をロンドンで過ごした経験を持つSEEDAは、バイリンガルスタイルのキレのあるラップでストリートの詩情を切り取ってきました。2006年の『花と雨』、2007年の『街風』といった歴史的名盤を生み出し、日本のラップゲームを一変させた存在です。
この「Nakamura Remix」では、自身のロンドンでの経験を活かし、UK出身のアーティストたちとの化学反応を生み出しています。
ralph(ラルフ)
1998年横浜生まれのralphは、日本では珍しいUKグライムやドリルスタイルを昇華したラッパーとして知られています。2019年のデビュー以来、その独特のスタイルで注目を集め、2020年にはABEMAの「ラップスタア誕生」で優勝を飾りました。
ralphの特徴:
- グライムやドリルを昇華したスタイル
- 切れ味鋭いライミングとダークな世界観
- プロデューサーチームDouble Clapperzとの長年のコラボレーション
重要なのは、ralphは自身をグライムやドリルを代表するMCだとは思っておらず、純粋にカッコいいと思う音楽を追求しているという姿勢です。音楽的な文脈や歴史についてはそれほど詳しくないと公言していますが、「音」を研究することが好きで、グライムとUKドリルの構造を独自に解析してオリジナルなラップを生み出しています。
2023年には「Get Back」がヴァイラル・ヒットし、その人気はさらに拡大。多数の客演をこなし、日本のヒップホップシーンにおいて欠かせない存在となっています。
Kraftykid(クラフティキッド)
イギリス・ロンドンのハックニー出身のKraftykidは、グライム/ドリルの本場で活動するラッパー、プロデューサー、ソングライターです。
日本との繋がりも深く、SEEDAが主宰するYouTube番組「ニート東京」にゲストとして出演したこともあり、後にインタビュアーとしても活動。GQ Japanにも取り上げられるなど、日本のメディアからも注目を集めています。
本場ロンドンのストリートで培われたスキルと、日本のシーンへの理解を持つKraftykidの参加は、このリミックスに本物のUKドリルの空気感をもたらしました。
ドリルミュージックとは
ジャンルの特徴
ドリルミュージックは、2010年代初頭にシカゴのサウスサイドを起源として広まったヒップホップのサブジャンルです。UKドリルは2012年(もしくは2014年)にサウスロンドンで誕生し、シカゴドリルとUKのギャングスタラップの影響を受けて発展しました。
UKドリルの特徴:
- BPM約138-151の速いテンポ
- 付点八分音符のスネアパターン
- スライディングベースとハードキック
- ダークで緊張感のあるメロディ
- グライム、UKガレージ、ダンスホール、ドラムンベースなどの影響
UKドリルは、グライムから影響を受けた808と速いテンポのスネアが特徴的で、シカゴドリルやブルックリンドリルとは異なる独自の進化を遂げています。
楽曲の魅力
世代と国境を超えたコラボレーション
この「Nakamura Remix」の最大の魅力は、日本のレジェンドSEEDA、日本の新世代を代表するralph、そしてUKドリルの本場ロンドンからKraftykidという、異なるバックグラウンドを持つ三者が一つの楽曲で共演していることです。
それぞれのアーティストが持つ独自のスタイル:
- SEEDA: バイリンガルラップと磨き抜かれたスキル
- ralph: 日本でのグライム/ドリルの先駆者としての独自の解釈
- Kraftykid: 本場ロンドンの正統派ドリルスタイル
これらが見事に調和し、一つの作品として完成度の高い仕上がりとなっています。
ミュージックビデオの演出
RepYourSelfのMESSがディレクションを担当したミュージックビデオは、細かく移り変わるカットとスピード感が特徴的です。楽曲の持つドリルの空気感を存分に引き立たせる映像表現となっており、視覚的にも楽曲の世界観を強化しています。
衣装にはAwesome boyやkZmといった日本のファッションシーンを代表するブランドが起用され、音楽だけでなくビジュアル面でも日本とUKのカルチャーが融合しています。
日本におけるドリルミュージックの展開
シーンの発展
日本におけるドリルミュージックは、ralphをはじめとする先駆者たちによって徐々に認知度を高めてきました。従来のブームバップやトラップとは異なる、UKからの新しいサウンドの流入は、日本のヒップホップシーンに新たな選択肢をもたらしました。
SEEDAのような重鎮がドリルミュージックに取り組むことで、ジャンルとしての正当性と芸術性が認められ、より多くのアーティストが挑戦するきっかけとなっています。
文化的意義
この楽曲は、単なる音楽的なコラボレーションを超えて、日本とイギリスのストリートカルチャーを繋ぐ架け橋としての役割も果たしています。SEEDAの幼少期のロンドン経験、ralphのUKサウンドへの傾倒、Kraftykidの日本シーンへの関わりという、それぞれの繋がりが重なり合って実現した作品と言えるでしょう。
リリース後の反響
チャート成績
iTunes Storeのヒップホップ/ラップ部門で日本16位を記録し、Spotifyの「BADASSVIBES presents TOKYO KIDS」や「The Sound of J-Rap」などの公式プレイリストにも選出されました。
ファンからの評価
ファンからは「日本とUKの最高峰の融合」「ドリルビートの上で三者三様のスタイルが炸裂」「ralphとKraftykidの化学反応がヤバい」といった声が多く寄せられています。
特にドリルミュージックのファンからは、本場ロンドンのKraftykidと日本のアーティストが共演したことで、より本格的なUKドリルサウンドが日本で聴けるようになったと高く評価されています。
ドリルの未来と「Nakamura Remix」の位置づけ
ジャンルの可能性
ドリルミュージックは、シカゴからロンドン、ニューヨーク、そして世界中に広がり、BBCが2021年に「グローバルユースのサウンド」と表現したように、国際的なムーブメントとなっています。
「Nakamura Remix」は、この世界的な流れの中で、日本のヒップホップシーンがいかにしてグローバルな潮流と接続し、独自の進化を遂げているかを示す重要な作品です。
レジェンドと新世代の対話
SEEDAのような2000年代から活躍するレジェンドが、ralphのような新世代の先駆者、そしてKraftykidのような海外アーティストと共演することで、世代と国境を超えた対話が生まれています。
これは単なるトレンドへの便乗ではなく、常に進化を続けるSEEDAの姿勢と、新しいサウンドを貪欲に取り入れる日本のシーンの柔軟性を示しています。
まとめ
SEEDA『Nakamura Remix FT ralph, Kraftykid』は、日本のヒップホップレジェンドと新世代、そしてUKドリルの本場ロンドンのアーティストが結集した、国境を越えたコラボレーションの傑作です。
ghostpopsのプロダクション、BACHLOGICのミックス・マスタリング、そして三者三様のラップスタイルが融合し、ドリルミュージックという新しいサウンドを日本のリスナーに届けました。
この楽曲は、日本のヒップホップシーンがいかにしてグローバルな音楽潮流と対話し、独自の表現を生み出しているかを示す重要な作品として、シーンの歴史に刻まれるでしょう。
もしまだこの楽曲を聴いたことがない方は、ぜひオリジナルの「Nakamura」から聴いて、リミックスバージョンでの三者の化学反応を体感してみてください。日本とイギリス、レジェンドと新世代が交差する瞬間を、その耳で確かめてほしいと思います。

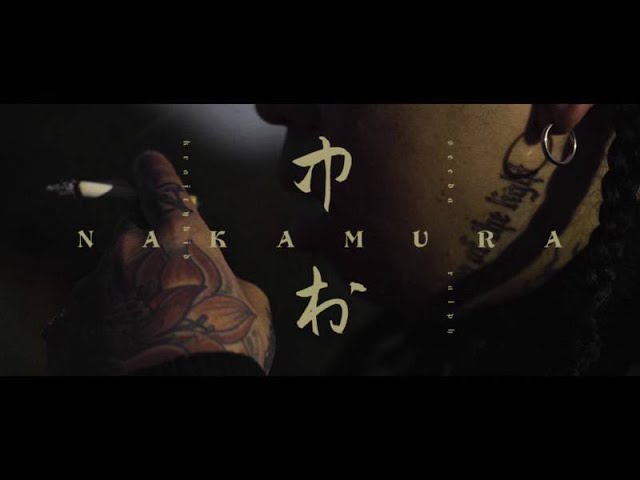



コメント