はじめに – 地元への想いが結晶化した傑作
2022年1月12日、愛知県知立市出身のラッパー・C.O.S.A.が、約7年ぶりの単独名義フルアルバム『Cool Kids』をリリースした。このアルバムは、単なる音楽作品の枠を超えて、一人の男性が父親となり、過去の自分と向き合いながら新たな表現領域に踏み込んだ記念碑的作品となった。
C.O.S.A.とは何者か – 愛知が生んだストーリーテラー
C.O.S.A.は1987年生まれ、愛知県知立市出身のラッパー兼プロデューサーである。12歳で歌詞を書き始め、16歳から名古屋市のクラブで活動を開始した。キャデラックのローライダーに乗っていた6歳上の姉の影響で深くヒップホップにのめり込んだ彼の音楽的ルーツは、幼少期の家族環境にまで遡る。
彼のファーストアルバム『Chiryu-Yonkers』(2015年)は、ファーストアルバムにしてクラシック(歴史に残る名盤)と評される実力の持ち主で、ライブには全国からファンが集まる。地元愛に溢れる楽曲制作でも知られ、楽曲「6号公園」、「桜町Weekender」、そして歴史に残る名盤「知立Babylon Child」には、すべて西三河の地名を使用している。
アルバム『Cool Kids』の誕生背景 – 父親の視点から見た過去
『Cool Kids』というタイトル曲の誕生には、深い個人的な体験が関わっている。C.O.S.A.は楽曲制作時のエピソードについて「”Cool Kids”を書いた時も、自分が毎日昔の通学路と同じ道を通るんですけど、いつも一人で帰ってる女の子がいたんですよ。いっつもその子一人なんですよね。『あの子また一人でいるわ』と思いながら何日か見てて。俺も小学校低学年の時にあまり友達がいなかったんで、一人で帰ってたんです。それを思い出して。その時に思ったのが、自分と重ねてどうとかじゃなくて、自分の娘がああなったら嫌だなっていう風に思って」と語っている。
「その時に自分を振り返る曲っていうのも”Chiryu-Yonkers”とかを書いた時と今では思うことが全然違うんだなと思って。自分のことというより娘がどうこうって思うようになったんで。それでもうちょっと自分の昔のこととか、自分のことを違う表現で歌えるのかもしれないと思って”Cool Kids”を書いたんですよ。奥さんと娘と三人でいる時間が一番長いので、それがアルバムとしてのきっかけだったと思いますね。」
音楽的特徴とプロダクション – 極限まで研ぎ澄まされたサウンド
今作に引き込まれたのは歌詞と音、双方の組み合わせの妙によるところが大きい。リズムは正統派のブーンバップだったりダークなトラップだったりするが、いずれにしても先述したように音数はタイトに絞り込まれており、そのぶんビートの一打一打の輪郭がくっきりと浮き彫りになっている。
また音の隙間に漂うひんやりとした緊張感も手伝い、総体はスタイリッシュな仕上がりでありながら、聴き心地はズシンと重い。プロデュース陣にはRamza、Ryo Kobayakawa、JJJに加え、Rascalをはじめとした海外ビートメイカーが名を連ねている。
特に印象的なのは冒頭”GZA Intro”の図太く際立ったベース音で、その一音目でこめかみに鮮烈な一発を食らった気分になる。プロデューサーはRamza。最小限どころか本来必要な音すらも削ぎ落していそうな音数で、それゆえに各音の存在感が際立つ点である。
リリック・アプローチの進化 – 説明的ではない巧妙な表現
C.O.S.A.は自身のリリック手法について「よくラッパーが書くのは、どこかに行って、その旅のことを書いたりしますよね。日記みたいなラップっていうか。それは自分はあんまり好きじゃなくて。例えば”Mikiura”とか”1AM in Asahikawa”とかは、その土地で思ったことについて書いてはいるんですけど、日記的な『ここで何があって、誰に会って』っていうラップじゃなくて、何を表現したいのかっていうのを表せるように、説明的にならないようにしています。」と語っている。
“Cool Kids”だと「デカいアメ車が~」っていうところはアメ車とかが地元にあったんだろうなっていうのは想起出来るが、そこからNate Doggがいないってラインでまた別のものに繋がるという巧妙な連想技法が用いられている。
サウンドの質感と世界観 – 柔と剛の絶妙なバランス
今作での C.O.S.A.は存在を誇示してはいるが、あからさまに暴力的な素振りはない。その目は近くを見ているようで遠いようでもあり、武骨な中にも常に何処か翳りを感じさせる。
様々な来事、様々な感情が絡み合った上で彼という人間が成り立っているわけで、その複雑さを綴った歌詞にリアリティを持たせるためには、サウンド面においても「柔」と「剛」を上手く両立してニュアンスを深める必要があった。彼は楽曲ごとにその配分を微調整し、なおかつ余計な装飾を徹底的に削ぎ落とすことで、今作を十分に説得力のある内容に仕立てている。
KID FRESINOとの対比 – 正反対のアプローチ
興味深いのは、共演も多いKID FRESINOとの音楽的アプローチの違いである。この両者、ラッパーとしてのスタイルや音楽性のベクトルは正反対だなと、今作を聴いて改めて思った。KID FRESINOはロックバンド編成で楽曲を制作したり、ヒップホップのジャンル外からもゲストを多数招聘したり、エレクトロニックなトラックにしても実験的な曲構成のものが多いなど、ヒップホップの可能性を押し広げよう、定型を打ち破ろうという気概があるのに対し、C.O.S.A.はより正統派なアプローチを採っている。
そのサウンドの中でC.O.S.A.自身のラップも明確な存在感を放ち、言葉の意味を着実に聴き手に伝えることが第一義、韻は踏むべき時に踏めばいいといった体で、自身の出で立ちから今現在の思い、内に浮かぶ優しさから憂いまで、とにかく彼という存在丸ごとを投げかけてくる。このスタンスもまた、ラップから意味をなるべく排除してトラックと同化させようとしていたKID FRESINOとは正反対だ。
制作過程と技術的側面
ミックスはD.O.I. for Daimonion Recordings、マスタリングはTatsuya Sato (The Mastering Palace, New York City)が手がけた。また、M3にはNatsuhiko Muraokaが追加でキーを担当し、M10にはDJ ZAIがカットを担当するなど、細部にまでこだわった制作体制が組まれた。
業界での評価と影響
個々の音、個々の言葉の全てが力強い。というように、言葉とリズム。ヒップホップという音楽を構成する主要素しかここにはないが、その主要素を純化、先鋭化させる手つきに容赦がなく、これはこれでまたヒップホップの最新型だと痛感させられる。
地元への変わらぬ愛情 – 知立への想い
C.O.S.A.は地元について「知立は東海道の宿場町で、どこに行くにも交通の便がいい。飲食店も『とんかつの浜田』や『バーグマン』など隠れたおいしい店がある。今の地元が好きだから、変わってほしいと思わない。」と語り、「仕事で東京から新幹線で帰るときに三河安城駅が見えると、本来の自分に戻った気がします」と地元愛をのぞかせている。
結論 – 新たなフェーズへの扉
C.O.S.A.の強さも脆さも愛情も痛みも、喜怒哀楽全てが彼のHIPHOPとして表現された作品である。『Cool Kids』は、単なる音楽アルバムの域を超え、一人の人間の成長と内面的変化を丁寧に描き出した作品として、日本のヒップホップシーンにおいて重要な位置を占めている。
父親としての新たな視点を得た C.O.S.A.が、過去の自分と向き合いながらも未来への希望を込めて制作したこの作品は、彼のキャリアにおける新たなフェーズの始まりを告げる記念碑的な1枚となった。地元愛と家族愛、そして音楽への真摯な姿勢が結晶化したこのアルバムは、聴く者の心に深く刺さる珠玉の作品として、長く語り継がれることだろう。



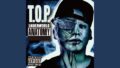

コメント