はじめに
「残念です ~相模、横浜、川崎編~ (feat. 林鷹 & STICKY)」は、神奈川県相模原市を代表するラッパーNORIKIYOが、横浜の林鷹(GANGSTA TAKA)と川崎のSTICKY(SCARS)を客演に迎えた楽曲です。2011年にリリースされたこの曲は、神奈川の三都市——相模、横浜、川崎——それぞれのシーンを代表するラッパーたちが集結した、まさに「神奈川オールスター」とも言える一曲です。
神奈川三都市の代表が集結
この楽曲のタイトル「残念です ~相模、横浜、川崎編~」が示す通り、神奈川県の三つの重要なヒップホップシーンを代表するラッパーが共演しています:
相模原 – NORIKIYO
NORIKIYOは神奈川県相模原市を中心に活動するヒップホップユニット、SD JUNKSTAのリーダーです。1999年頃、地元の仲間達(Bron-K、TKC)とSD JUNKSTAを結成し、当初はK-NEROという名前でトラックメイカーとして活動していました。
2007年にリリースした1stソロアルバム『EXIT』は、「THE SOURCE」誌による「BEST OF JAPANESE RAP 2007」で第3位、日本語ラップWEBマガジン「COMPASS」では「年間最優秀アルバム」に選出されるなど、高い評価を受けました。
横浜 – 林鷹(GANGSTA TAKA)
林鷹は横浜の元町出身、伊勢崎町をレペゼンするラッパーです。CLUB CIRCUS、THE BRIDGE YOKOHAMA、CLUB HEAVENでのパーティーや黒人中心のパーティーでMCとして頭角を現しました。
SEEDAとDJ ISSOによる伝説的なMIX CDシリーズ『CONCRETE GREEN』にGANGSTA TAKAとして客演したことで一気に注目を集め、後にSCARSの正式メンバーとしてもクレジットされるようになります。
川崎 – STICKY(SCARS)
STICKYは川崎を代表するヒップホップグループSCARSの主要メンバーです。メンバーの中でも一際クールに冷めた視点で、淡々と世の中にツバを吐くように言葉をスピットするスタイルが支持されました。
不信感や絶望感、そして孤独感などをコンセプトにしたラップを売りにしており、コアなファンが多いことでも知られています。2009年にリリースした1stソロアルバム『WHERE’S MY MONEY』では、人生のすべてに付きまとう「金」をコンセプトに、漢、KENJI YAMAMOTO、林鷹、BRON-K、鬼、SEEDAといった豪華なフィーチャリングアーティストを迎えました。
2011年というタイミング
「残念です ~相模、横浜、川崎編~」は、NORIKIYOの3rdアルバム『メランコリック現代』(2011年6月10日リリース)に収録されました。
このアルバムはインディーズながらオリコンデイリーチャート(総合)で16位を記録するなど、NORIKIYOのキャリアにおいて重要な作品となっています。
2011年は、NORIKIYOが定期的にシングルをリリースし始めた年でもあり、この「残念です」もその一環としてリリースされました。同年末にリリースした「ありがとう、さようなら」は曲とともにMVが話題になるなど、NORIKIYOの活動が活発化した時期でした。
「残念です」というタイトルの意味
この楽曲のタイトル「残念です」——一見ネガティブに聞こえるこの言葉には、どのような意味が込められているのでしょうか。
神奈川の三都市を代表するラッパーが集まったこの曲で歌われる「残念」は、おそらく以下のような複数の意味を持っています:
- ストリートで生きる現実への諦観
- 社会に対する皮肉
- 変わらない日常への失望
- それでも生き続けなければならない矛盾
「残念です」という言葉の裏には、ストリートのリアルと、そこで生きる者たちの複雑な感情が込められています。
神奈川ヒップホップシーンの繋がり
この楽曲が実現した背景には、神奈川のヒップホップシーンの深い繋がりがあります。
NORIKIYOは2005年頃、SEEDAとDJ ISSOのMIX CD『CONCRETE GREEN』に参加し話題をさらいました。そして2006年にはSEEDAの名盤『花と雨』に客演で参加(「ガキの戯言」にK-NERO名義で、STICKYとも共演)するなど、SCARSファミリーとの繋がりも深いラッパーです。
林鷹もまた『CONCRETE GREEN』にGANGSTA TAKAとして参加し、後にSCARSメンバーとなります。そしてSTICKYはSCARSの中心メンバー——この三人の繋がりは、単なる客演の域を超えた、神奈川ヒップホップシーンの絆を象徴しています。
SD JUNKSTAとSCARSの関係
NORIKIYOが率いるSD JUNKSTAと、STICKYが所属するSCARSは、神奈川のヒップホップシーンにおける二大グループです。
SD JUNKSTAからはBRON-Kが林鷹のソロ楽曲に参加し、NORIKIYOも数々のSCARS関連の楽曲に参加するなど、両グループの交流は深いものがあります。
「残念です ~相模、横浜、川崎編~」は、そんな神奈川シーンの繋がりを象徴する楽曲でもあるのです。
「残念です」シリーズの存在
興味深いことに、NORIKIYOは「残念です ~相模原編~」という楽曲も制作しています。これは2013年のEP『断片集』に収録されており、地元相模原にフォーカスした内容となっています。
「相模、横浜、川崎編」が神奈川全体を俯瞰する楽曲だとすれば、「相模原編」は地元により深く踏み込んだ楽曲と言えるでしょう。この「残念です」というテーマは、NORIKIYOにとって重要なコンセプトの一つだったようです。
STICKYの参加が持つ意味
2021年1月にSTICKYが逝去したことを考えると、この楽曲は非常に貴重な記録となっています。
STICKY、林鷹、NORIKIYOという神奈川を代表する三人のラッパーが共演したこの楽曲は、もう二度と実現することのない組み合わせです。STICKYのクールで淡々としたラップは、この曲でも健在で、彼の遺した数少ない客演作品の一つとして、ファンにとって特別な意味を持っています。
神奈川のストリートカルチャー
「残念です ~相模、横浜、川崎編~」は、神奈川のストリートカルチャーを象徴する楽曲です。
相模原のSD JUNKSTA、横浜の林鷹、川崎のSCARS——それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながらも、同じ神奈川という土地で育ち、ストリートのリアルを音楽に昇華させてきたラッパーたちです。
この楽曲では、三都市それぞれの空気感、生活感、そして「残念」な現実が描かれているはずです。
2011年当時のシーン
2011年は、日本のヒップホップシーンにとって重要な年でした。東日本大震災が発生し、社会全体が大きく揺れた年でもあります。
そんな時期にリリースされた「残念です」というタイトルの楽曲は、単なる個人的な感情だけでなく、時代の空気も反映しているのかもしれません。
NORIKIYOのキャリアにおける位置づけ
『メランコリック現代』は、NORIKIYOにとって重要なアルバムでした。2008年の『OUTLET BLUES』から3年ぶりのリリースとなったこのアルバムは、インディーズながらオリコンデイリーチャート(総合)で16位を記録しました。
「残念です ~相模、横浜、川崎編~」は、そんなアルバムの中でも、神奈川シーンの繋がりを示す重要な一曲として位置づけられます。
林鷹とSTICKYの化学反応
林鷹とSTICKYは、共にSCARSに関わるラッパーですが、そのスタイルは対照的です。
林鷹は横浜の元町・伊勢崎町という、ある意味華やかなエリアをバックグラウンドに持ち、黒人中心のパーティーで頭角を現したラッパーです。一方、STICKYは川崎のストリートで育ち、不信感や絶望感をコンセプトにした、よりダークなラップを展開します。
この二人がNORIKIYOという相模原のラッパーのトラックで共演することで、神奈川の多様性が表現されています。
「残念です」に込められた諦観と希望
「残念です」というタイトルは、一見するとネガティブです。しかし、ヒップホップにおいて「残念」という感情は、単なる敗北ではありません。
それは現実を直視した上での諦観であり、それでも前に進もうとする意志の表れでもあります。相模、横浜、川崎——三つの都市で生きるラッパーたちが「残念です」と歌うとき、そこには複雑な感情が交錯しています。
まとめ – 神奈川ヒップホップの結晶
「残念です ~相模、横浜、川崎編~ (feat. 林鷹 & STICKY)」は、神奈川のヒップホップシーンを象徴する楽曲です。
相模原のNORIKIYO、横浜の林鷹、川崎のSTICKY——三都市を代表するラッパーたちが集結し、それぞれの「残念」を歌い上げたこの曲は、神奈川ストリートのリアルを凝縮した作品と言えるでしょう。
2011年にリリースされたこの楽曲は、今となってはSTICKYの遺した貴重な客演作品の一つでもあります。彼のクールで淡々としたラップ、林鷹のストリート感溢れるスタイル、そしてNORIKIYOの鮮明な情景描写——三者三様のラップが融合したこの曲は、神奈川ヒップホップの結晶です。
「残念です」——この言葉に込められた諦観と、それでも生き続ける強さ。それこそが、ストリートで生きるラッパーたちのリアルなのです。

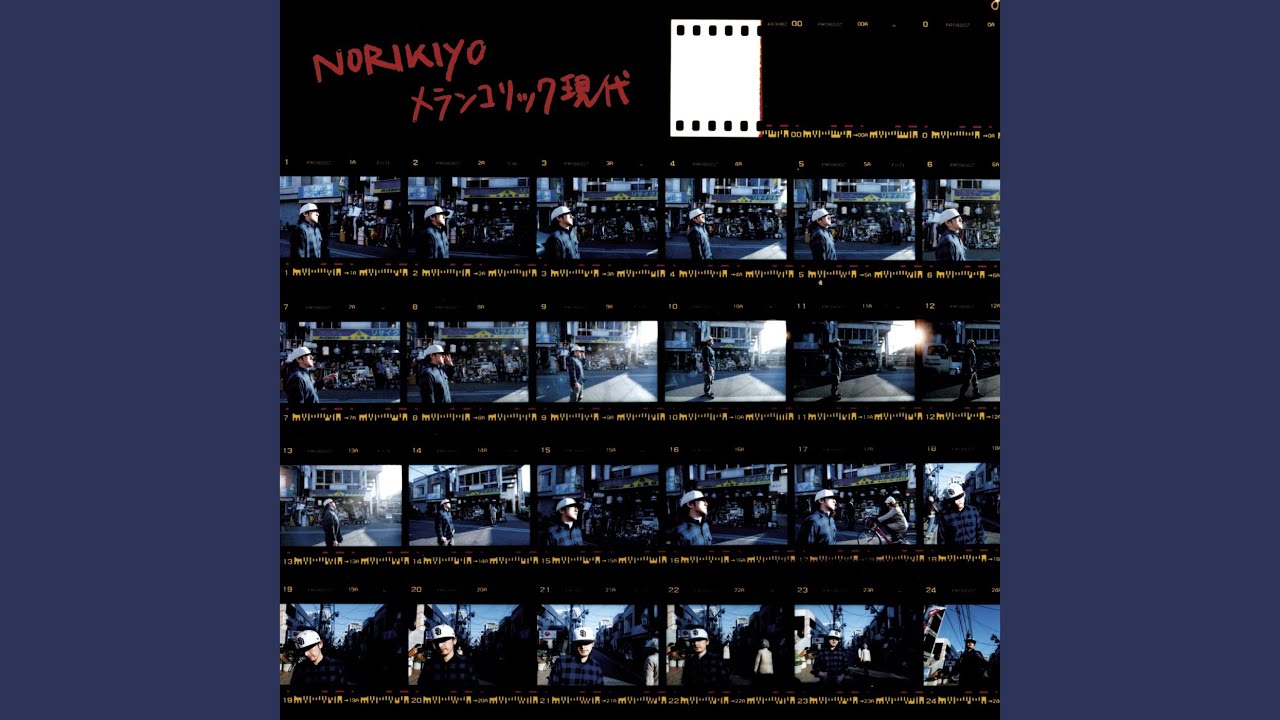



コメント